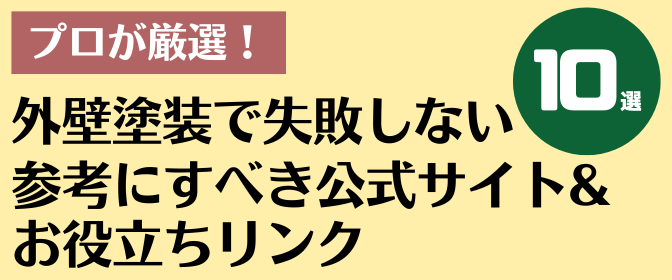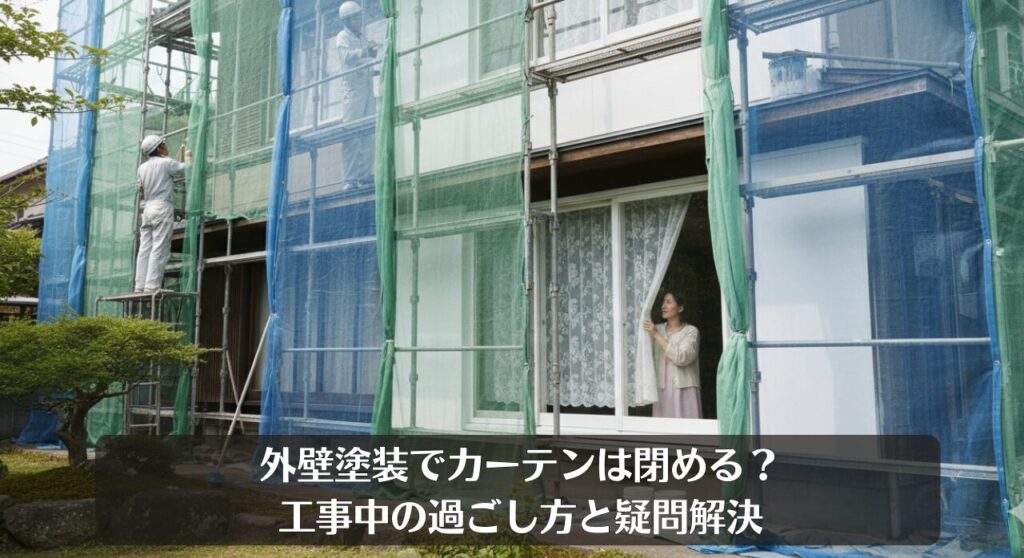
ご自宅や賃貸アパートの外壁塗装が決まった際、「外壁塗装中はカーテンを閉めるべきか」と悩む方は少なくありません。
工事中は足場が組まれ、職人さんが窓のすぐ近くで作業を行うため、普段通りの生活とは勝手が異なります。
職人さんの視線が気まずいと感じたり、家にいる時間の過ごし方に困ったりすることもあるでしょう。
また、差し入れ置き場所は必要か、職人さんのトイレはどうなるのか、どのタイミングでカーテンを閉めるべきか、あまり要望を伝えるとうるさい客と思われないかなど、疑問は尽きません。
特に窓を開けられない期間は、換気もできず外壁工事ストレスを感じやすい時期です。
この記事では、そうした外壁塗装にまつわる疑問や不安を一つひとつ解消し、工事期間中を少しでも快適に過ごすための具体的な方法を詳しく解説します。
記事のポイント
- 外壁塗装中にカーテンを閉めるべき具体的な理由(プライバシー保護・防犯)
- 工事中の騒音や臭いによるストレスの具体的な軽減策
- 職人さんへの差し入れやお茶出しの必要性と、スマートな対応方法
- 工事期間中の洗濯や換気など、日常生活における具体的な注意点
- 1. 外壁塗装工事でカーテンを閉めるべき理由とタイミング
- 1.1. 家にいる時のプライバシー保護
- 1.2. 職人さんと目が合う気まずい瞬間
- 1.2.1. 日中の明るさを確保したい場合は「レースカーテン」を活用
- 1.3. カーテンを閉める最適なタイミング
- 1.3.1. 特にカーテンを閉めておきたい作業工程
- 1.4. 賃貸アパートでの注意点
- 1.4.1. 賃貸アパート特有のストレスと事前確認
- 1.5. 窓を開けられない期間の対策
- 1.5.1. 換気はどうする?
- 1.5.1.1. 換気扇の使用(要注意)
- 1.5.1.2. エアコンの使用(要事前相談)
- 1.5.1.3. 空気清浄機
- 1.5.2. 洗濯物はどうする?
- 2. 「外壁塗装に工事期間中はカーテンを閉める?」以外の疑問
- 2.1. 工事期間中のストレスの原因と対策
- 2.2. 工事中の快適な過ごし方
- 2.2.1. ストレスを避けるための具体的な過ごし方
- 2.2.1.1. 外出の計画を立てる (最も有効)
- 2.2.1.2. 耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの活用
- 2.2.1.3. 作業のない場所で過ごす
- 2.2.2. 健康が最優先:一時的な仮住まいも選択肢に
- 2.3. 職人のトイレの心配は必要か
- 2.3.1.1. 仮設トイレを設置する
- 2.3.1.2. 近隣の公共トイレを利用する
- 2.4. 差し入れの置き場所は必要?
- 2.4.1. もし差し入れをする場合のスマートな方法
- 2.4.1.1. クーラーボックス・ポットの活用
- 2.4.1.2. お茶代として包む
- 2.5. うるさい客と思われない過ごし方
- 2.5.1. 良好な関係を築くためのコミュニケーション術
- 2.5.1.1. 挨拶とねぎらいを心がける
- 2.5.1.2. 要望は必ず「現場責任者」に伝える
- 2.5.1.3. 感情的にならず「相談」ベースで話す
- 2.5.1.4. 工程表を理解する姿勢を見せる
- 2.5.1.5. 事前に片付けを済ませておく
- 2.6. 「外壁塗装期間中はカーテンを閉めるか?」の最終判断
外壁塗装工事でカーテンを閉めるべき理由とタイミング
外壁塗装の期間中、多くの方が悩む「カーテン問題」。結論から言えば、閉めておく方がメリットは大きいです。
このセクションでは、なぜカーテンを閉めるべきなのか、その具体的な理由と、生活への影響を最小限にするためのタイミングについて解説します。
- 家にいる時のプライバシー保護
- 職人さんと目が合う気まずい瞬間
- カーテンを閉める最適なタイミング
- 賃貸アパートでの注意点
- 窓を開けられない期間の対策
家にいる時のプライバシー保護
外壁塗装では、周囲に足場を設置し、飛散防止・落下防止・近隣配慮のために飛散防止ネット(メッシュシート)を張るのが一般的です。
これにより、職人は2階・3階の窓と同じ高さ・近距離で作業します。プライバシー配慮のため、日中はレース(遮像・ミラーレース等)を閉める運用が安心です。
職人さんに覗くつもりがなくても、室内の様子(例えば、くつろいでいる姿や着替えの瞬間など)が意図せず見えてしまう可能性は常に存在します。
さらに深刻な問題として、防犯上のリスクが挙げられます。足場は侵入リスクを高める要因になります。
複数の県警は「2階へ上がる足場(物置・室外機等を含む)を作らない」「死角を作らない」などの対策を案内しています。
工事中は普段使わない高所窓も含めて戸締まりを徹底しましょう。県警は死角の抑制・センサーライト等も推奨しています。
足場やネットで周囲の見通しが落ちる期間は、在宅感の演出・タイマー照明も抑止に有効です。
カーテンを閉めておくことは、室内の間取りや貴重品の有無、家族構成や在宅状況といった情報を外部から分かりにくくする効果があり、犯罪を企む者に対する心理的な抑止力となります。
(参考:「空き巣」の防犯対策 | 侵入盗に注意 | 千葉県警察)

職人さんと目が合う気まずい瞬間
プライバシー保護とも関連しますが、カーテンを開けていると、ふとした瞬間に窓の外で作業している職人さんと目が合ってしまうことがあります。
これは、居住者側が「見られた」と感じるだけでなく、職人さん側にとっても非常に気まずいものです。
多くの職人さんは「中を覗いている」と誤解されたくないため、居住者の気配を感じるとかえって気を遣い、作業に集中できなくなるケースもあります。
カーテンを閉めておくという一つの行動は、お互いの心理的な負担を軽減し、職人さんが作業に集中できる環境を整えるための「配慮」とも言えます。
日中の明るさを確保したい場合は「レースカーテン」を活用
「とはいえ、日中ずっと厚手のカーテンを閉めていると部屋が暗くなって滅入ってしまう」という方も多いでしょう。
その場合は、厚手のカーテンは開け、レースカーテンだけでも必ず閉めておくことをおすすめします。
特に、外からの光を取り入れつつ室内を見えにくくする「ミラーレースカーテン」や「遮像(しゃぞう)レースカーテン」は、日中のプライバシー対策として非常に有効です。
選び方の目安として、日中の採光を確保しつつ視線を遮るなら「ミラー」、夜間(室内が明るい状態)も含めて常に見えにくさを優先するなら「遮像」を選ぶと失敗が少ないです。
これ一枚あるだけでも、外からの視線は大幅に遮断できます。

カーテンを閉める最適なタイミング
「工事期間中、本当にずっと閉めっぱなしにしないといけないの?」と疑問に思うかもしれません。
カーテンを特に閉めておくべきタイミングと、比較的開けやすいタイミングは、業者の作業内容によって異なります。
まず、施工業者から必ず「工事工程表(スケジュール表)」をもらいましょう。これを見れば、いつ、どのような作業が行われるかが一目で把握できます。
特にカーテンを閉めておきたい作業工程
- 足場の設置・解体時
家の周りを作業員が頻繁に行き来します。金属音が響くため、音のストレスも大きい時期です。 - 高圧洗浄時
強力な水圧で壁の汚れを落とすため、水しぶきや汚れた水が窓に激しく叩きつけられます。窓の隙間から水が侵入し、カーテン自体が汚れるのを防ぐ意味もあります。 - 塗装作業中(下塗り・中塗り・上塗り)
窓のすぐ近くで刷毛やローラーを使った作業が行われます。最も視線が気になる工程であり、塗料のミストが隙間から入る可能性もゼロではありません。
逆に、塗料の乾燥を待つだけの時間(工程表の「乾燥養生」など)や、その日の作業が早く終わった夕方以降(通常17時頃)であれば、カーテンを開けて換気や採光をしても問題ありません。
休工日は開放可ですが、休工日は現場により異なります。
外壁塗装は「土曜は作業・日曜は休工」の運用が比較的多い一方、土日とも作業/両日休工の現場もあります。休工日の有無は現場によって異なるため、工程表と当日アナウンスの確認を前提に判断してください。
「今日はカーテンを開けても大丈夫ですか?」と、朝の作業開始時に現場の責任者の方に一声かけて確認するのが一番確実です。柔軟に対応してくれることも多いです。

賃貸アパートでの注意点
ご自宅が賃貸アパートの場合、戸建て住宅とは異なる特有の注意点があります。最大の違いは、工事の実施決定権がオーナーや管理会社にある点と、隣室との距離が非常に近い点です。
アパートの外壁工事で生じる主なストレスは、やはり「騒音」「塗料の臭い」「生活空間の制限(暗さや人の出入り)」です。
特に在宅勤務(テレワーク)をしている方や、小さなお子様・ペットがいるご家庭では、日中の騒音や臭いが大きな負担になることがあります。
賃貸アパート特有のストレスと事前確認
分譲マンションとは異なり、賃貸アパートの入居者には工事の実施を原則として拒否する権利がありません。
これは、建物を維持・修繕することがオーナー(貸主)の義務(民法606条)とされており、入居者(借主)はそれに協力するよう求められるためです。
そのため、工事が始まると「我慢する」しか選択肢がなくなりがちですが、大規模修繕は住環境に影響するため、オーナー側には「事前告知」や「入居者への配慮」が望ましいとされています。
(参考:賃貸住宅トラブルQ&A|公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会) 公式サイト)
ストレスを最小限にするため、工事の通知が来たら、すぐに以下の点を確認しましょう。
- 詳細なスケジュール: 騒音や臭いが特にひどい日を把握する。
- 使用する塗料: 臭いが少ない水性塗料を使用してもらえないか、管理会社経由で相談してみる。
- ベランダの使用制限: 洗濯物を干せない期間を正確に把握する。
事前に情報を得ることで、外出の計画を立てるなどの自衛策が取りやすくなります。
工事前にポストに投函される「工事のお知らせ」には必ず目を通し、作業スケジュール、洗濯物を干せない期間、窓の開閉制限などを正確に把握しておくことが、ストレス軽減の第一歩です。

窓を開けられない期間の対策
外壁塗装の工程の中で、最も生活への影響が大きいのが「養生(ようじょう)」の期間です。
養生とは、窓枠やガラス、ドア、エアコンの室外機など、塗料が付いてはいけない部分を専用のビニールシートやテープでぴったりと覆う作業を指します。
この養生がされている期間は、窓を物理的に開けることができなくなり、家が密閉状態に近くなります。
一般的に、高圧洗浄が終わった後の下地処理(ヒビ割れ補修など)の段階から、全ての塗装作業(上塗り)が完了するまでの約5日〜1週間程度が目安となります。
塗料の乾燥期間や工事が休みの日(休工日)は開放できる日もあるため、工程表で確認したり、当日朝に現場の監督へ「今日は開けられますか?」と可否を確認するのが一番確実です。
換気はどうする?
窓が開けられないため、室内の換気が著しく困難になります。特に塗料の臭いが室内にこもりやすくなるため、対策が必要です。
換気扇の使用(要注意)
臭いを排出しようとキッチンの換気扇を強く回すのは逆効果になることがあります。窓が密閉された状態で強制的に排気を行うと、室内の気圧が下がる「負圧」状態になります。
その結果、玄関ドアの郵便受けの隙間や、わずかな建物の隙間から、かえって外の塗料の臭いを強く室内に引き込んでしまうのです。換気扇の使用は最小限に留めましょう。
エアコンの使用(要事前相談)
エアコンは基本的に使用可能です。
ただし、室外機がビニールで完全に覆われ、空気の吸排気(すうはいき)が妨げられると故障の原因になるため、必ず事前に「工事中もエアコンを使いたい」と業者に伝えてください。
通常、室外機の動作を妨げないメッシュ状の専用カバー(飛散防止と吸気確保を両立できるもの)で養生してくれます。
空気清浄機
空気清浄機 室内の臭い対策として、空気清浄機を稼働させるのは効果的です。塗料の臭いの原因であるVOC(揮発性有機化合物)は、活性炭フィルターが吸着するのに適しているためです。
活性炭フィルターを搭載した機種(HEPAフィルターも付いていると粉じん対策にもなります)を、養生期間中を中心に連続運転するのが現実的です。
洗濯物はどうする?
養生期間中や塗装作業中は、塗料の飛散リスクがあるため、ベランダや窓の外に洗濯物を干すことは一切できません。この期間は、室内干しに完全に切り替える必要があります。
室内干しのスペースが足りない場合や、生乾きの臭いが気になる場合は、浴室乾燥機や除湿機、サーキュレーターを併用すると効率よく乾かせます。
シーツなどの大物が多い場合は、割り切ってコインランドリーの乾燥機を利用するのも賢い選択です。
洗濯物を外に干せない期間は、工程表でしっかり確認しておくか、朝、現場の担当者に「今日は干せますか?」と確認するのが確実です。

「外壁塗装に工事期間中はカーテンを閉める?」以外の疑問
外壁塗装中は、カーテンの問題以外にも「職人さんへの対応」や「日常生活の制限」など、細かな疑問や不安が次々と出てくるものです。
このセクションでは、そうした生活上の具体的な疑問について、一つひとつ丁寧にお答えします。
- 外壁塗装工事中のストレスの原因と対策
- 工事中の快適な過ごし方
- 職人トイレの心配は必要か
- 差し入れ置き場所は必要?
- うるさい客と思われない過ごし方
工事期間中のストレスの原因と対策
外壁工事の期間中、居住者は程度の差こそあれ、さまざまなストレスに直面します。その原因は多岐にわたりますが、主なものは「騒音」「臭い」「生活の制限」です。
これらの原因と、業者側ができる対策(または居住者側が依頼できる配慮)について、以下の表にまとめます。
これらのストレスを軽減するためには、施工業者との事前の綿密なコミュニケーションが何よりも重要です。
「いつ、どんな作業があり、どの程度の音や臭いが発生するのか」を詳細なスケジュール表や説明によって事前に把握し、心の準備をしておくことが最大の防御策となります。
不安な点は遠慮なく質問し、情報を共有してもらいましょう。
| ストレスの原因 | 具体的な状況 | 主な対策・配慮(業者側・居住者側) |
|---|---|---|
| 騒音 | 足場の設置・解体時の金属音 (カンカンという高い音) 高圧洗浄機のエンジン音 (継続的な大きな音) 下地処理の工具音 (ドリルやサンダーなど) | 業者:騒音が大きい作業日を事前にカレンダーで告知する。 業者:作業時間を日中の短時間に集中させる。 居住者:騒音日に外出の計画を立てる。(後述) |
| 臭い | 特に油性塗料(溶剤系)を使用する場合のシンナー臭。 窓が密閉され、臭いが室内にこもりやすい。 | 業者:臭いが比較的少ない水性塗料や弱溶剤塗料の使用を提案する。 居住者:契約前に使用塗料について確認・相談する。 居住者:空気清浄機(VOC対応)を準備する。 |
| 窓の開閉制限 | 養生により約1週間、窓が開けられず換気ができない。 閉塞感による精神的ストレス。 | 業者:換気のために開けたい窓(例:浴室やトイレ)を事前に伝え、開閉可能な特殊な養生をしてもらえないか相談する。 業者:養生の開始日と終了日を明確に伝える。 |
| 洗濯物の制限 | 全期間、または塗装・養生期間中は外干しが一切できない。 室内干しのスペースや臭いの問題。 | 居住者:室内干しスペースの確保、コインランドリーの利用計画を立てる。 業者:(まれに)近隣のコインランドリー情報の提供や、サービスチケットの配布。 |
| 生活空間の制限 | 足場と飛散防止ネットにより部屋が暗くなる。 人の気配が常にあり、落ち着かない。 駐車スペースが使えなくなる場合がある。 | 業者:進捗状況を定期的に報告し、いつ終わるかの見通しを明確にする。 業者:駐車場の移動先について事前に調整する。 居住者:日中はレースカーテンを活用し、照明をつけて明るく保つ。 |

工事中の快適な過ごし方
前述の通り、工事期間中は騒音や臭い、人の気配など、家にいること自体がストレスになりやすい特殊な環境です。
特に在宅で仕事や勉強、育児をされている方にとっては深刻な問題となります。可能であれば、以下のような過ごし方を検討し、心身の負担を軽減することをおすすめします。
ストレスを避けるための具体的な過ごし方
外出の計画を立てる (最も有効)
最も効果的な対策は、物理的にその場から離れることです。
工程表で特に騒音が大きいと予想される「足場設置日」や「高圧洗浄日」は、あらかじめ外出の予定を入れておくと心身ともに非常に楽になります。
図書館、カフェ、商業施設、日帰り温泉、友人宅などで過ごすのも良いでしょう。
耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの活用
在宅勤務などでどうしても家にいる必要がある場合、遮音性の高い耳栓や、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホン・ヘッドホンは必須アイテムです。
音楽を聴いたり、集中できる環境音を流したりするだけでも、工事の騒音ストレスは大幅に軽減されます。
作業のない場所で過ごす
工事は通常、家の四方を同時に行うわけではなく、「今日は南面」「明日は西面」といった具合に進みます。
朝、業者に当日の作業場所を確認し、なるべく作業場所から離れた部屋(例:北側で作業中なら南側の部屋)で過ごすようにするのも賢い方法です。
健康が最優先:一時的な仮住まいも選択肢に
ご家族に塗料の臭い(VOC)に敏感な方、アレルギー体質の方、妊婦さん、乳幼児、高齢者がいらっしゃる場合、健康への影響が懸念されます。
その場合は、無理をせず、工事期間中だけウィークリーマンションや実家などに一時的に仮住まいすることも真剣に検討する価値があります。健康は何物にも代えがたいものです。

職人のトイレの心配は必要か
工事が始まるにあたり、「工事中、職人さんから自宅のトイレを貸してほしいと言われないか」と心配される方が非常に多いですが、その必要は現代においてはありません。
現在の建設業界、特に優良なリフォーム会社では、コンプライアンスや衛生観念の向上により、施主様(お客様)宅のトイレを借りないのが絶対的な原則です。
職人さんたちも、お客様のプライベートな空間をお借りすることに強い抵抗感を持っています。
では、どうしているかというと、以下のいずれかの方法が一般的です。
仮設トイレを設置する
敷地内に余裕がある場合、施工業者がレンタルした仮設トイレを設置します。この場合、その設置場所については事前に業者から「どこに置かせていただけますか」と相談があります。
プライバシーの観点から、玄関やリビングの窓の正面を避け、人目につきにくい場所(例:敷地の隅など)を希望として伝えることは可能です。
近隣の公共トイレを利用する
都心部や住宅密集地で仮設トイレを置くスペースがない場合は、職人さんが作業の合間に、近隣のコンビニエンスストアや公園の公衆トイレを利用します。これが最も一般的なケースです。
したがって、施主様がトイレの心配をする必要は一切ありませんのでご安心ください。

差し入れの置き場所は必要?
「職人さんへのお茶出しや差し入れは、毎日すべき?」「差し入れ置き場所は必要?」これもまた、非常に多くの方が悩む問題です。
結論から言えば、「現代においては、差し入れは必須では全くない」というのが現状です。
これはあくまで「仕事」であり「ビジネス」です。差し入れの有無や内容によって、工事の品質が意図的に左右されることは、優良な業者であれば決してありません。
職人さんも、夏場の水分補給や休憩時の飲み物は、各自が水筒やペットボトルで持参するのが基本です。
とはいえ、昔の慣習で「何も出さないのは気が引ける」「寒い中・暑い中作業してくれてありがたい」という方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、義務感ではなく「感謝の気持ち」として、無理のない範囲で対応するのがスマートです。
もし差し入れをする場合のスマートな方法
もし感謝の気持ちとして何かを提供したい場合、毎日時間を決めてお盆でお茶を運ぶ…といった方法は、かえって職人さんに気を遣わせ、休憩のタイミングを縛ってしまう可能性があります。
以下のような方法が、双方にとって負担が少なく喜ばれます。
クーラーボックス・ポットの活用
夏場であればクーラーボックスに氷と数種類のペットボトル飲料(お茶、スポーツドリンク、水、缶コーヒーなど)を入れましょう。
そして、朝、作業開始前に「ご自由にどうぞ」と一声かけて分かりやすい場所に置いておきます。
冬場であれば、電気ポットとお湯、インスタントコーヒーやティーバッグ、紙コップをセットにして置くのも良いでしょう。
お茶代として包む
対応が難しい場合は、工事初日に「休憩の飲み物代に」と少額(3,000円〜5,000円程度)をポチ袋で現場責任者に渡すのもスマートな方法です。
多くの職人さんにとって、高価な差し入れよりも、朝夕の「おはようございます」「お疲れ様です」「寒い中ありがとう」といった温かい「ねぎらいの言葉」が一番の励みになるそうです。

うるさい客と思われない過ごし方
工事の品質を保ち、お互いに気持ちよく工事期間を終えるためにも、施工業者とは良好な関係を築きたいものです。
「要望を伝えたら、うるさい客(クレーマー)だと思われないか」と不安に思うあまり、当然の疑問や不具合を指摘できなくなっては本末転倒です。
大切なのは、相手もプロの人間であると信頼し、リスペクトを持って接すること、そして要望の伝え方に工夫をすることです。
良好な関係を築くためのコミュニケーション術
挨拶とねぎらいを心がける
前述の通り、これは基本中の基本です。顔を合わせた際に「お世話になります」「毎日お疲れ様です」と笑顔で声をかけるだけでも、現場の雰囲気は格段に良くなります。
要望は必ず「現場責任者」に伝える
これが最も重要です。気になる点(例:塗料が車に飛びそう、養生が甘い箇所がある)があった場合、作業中の職人さん個人に直接指示を出すのは絶対に避けてください。
指示系統が混乱し、トラブルの原因になります。必ず「現場監督」や「責任者」の方を呼んでもらい、その方にまとめて要望を伝えてください。
感情的にならず「相談」ベースで話す
「どうなってるんだ!」と頭ごなしに怒るのではなく、「こういう点が気になるのですが、どうにかなりませんか?」と相談・質問の形で伝えると、相手も冷静に対応しやすくなります。
工程表を理解する姿勢を見せる
工事には効率的な順序があります。工程表を無視して「あっちよりも先にこっちを塗ってほしい」といった要求は、現場を困らせる「うるさい客」と見なされがちです。
なぜその順序なのかを理解する姿勢も大切です。
事前に片付けを済ませておく
足場を組むスペース(建物の周囲1メートル程度)や、高圧洗浄・塗装を行うベランダの荷物(植木鉢、自転車、物置など)は、工事開始前に居住者側で片付けておくのがマナーです。
業者が動かすと破損のリスクもあり、作業の妨げになります。事前に片付けておくことで「工事に協力的である」という姿勢が伝わります。
もちろん、契約と違う、明らかな施工不良、約束が守られていない、といった正当なクレームについては、遠慮なく冷静に、しかし強く指摘して問題ありません。
大切なのは、過度な要求と、施主としての当然の権利の線引きをわきまえることです。

「外壁塗装期間中はカーテンを閉めるか?」の最終判断
- 外壁塗装中はプライバシー保護と防犯のためカーテンを閉めるのが基本
- 特に足場設置、高圧洗浄、塗装作業中は閉めておくことを推奨
- 日中の暗さが気になる場合はレースカーテンだけでも閉める
- 職人さんと居住者双方の「気まずい」状況を避ける効果もある
- 賃貸アパートの場合は特に騒音や臭いへの事前の対策把握が重要
- 「養生」期間中は窓が開けられず換気が制限される
- 窓を開けられない期間は室内干しやコインランドリーを活用する
- エアコン使用の可否は事前に業者へ確認し養生方法を相談する
- 外壁工事のストレスは騒音、臭い、生活制限が主な原因
- ストレス軽減には詳細な工程表の事前入手と確認が不可欠
- 騒音が大きい日は外出を計画するなど快適な過ごし方を工夫する
- 職人トイレの心配は不要で施主宅のトイレ使用は原則ない
- 差し入れやお茶出しは義務ではなく、あくまで気持ちの問題
- 差し入れはクーラーボックス利用や「お茶代」として渡す方法も
- 要望は現場の職人個人ではなく「責任者」に伝える
- 挨拶や事前の片付けが業者との良好な関係構築につながる